 |
 |
 |
| 覚法寺支部 加藤晶子 |
| 全てお題目で乗り切れた 私が信心に巡り会えたきっかけは、母が昭和三十一年十二月十五日に御本尊様を我が家にお迎えしたことです。病気がちの母は元気になりたい一心で入信しました。無学な母が私に、「お経を読みたい」と言うので、毎日一緒にオウム返しで勤行をしました。 ある日、母に「よい所に連れていってあげる」と言われ、一緒に出かけました。当時お寺がなかった和歌山に、月に一度、堺の本伝寺の御住職が出張御授戒に来てくださり、そこで私は御授戒をしていただきました。 翌年、母の元気になった姿を見て父も入信し、家族全員で御登山させていただきました。父は、「自分が死んだら総本山に墓を建ててほしい」と母に言ったそうです。その父が、昭和四十四年に亡くなり、下之坊の墓苑にお墓を持つことができました。 母は私に信心強盛な人と結婚するようにと、家族全員が学会の幹部をしている家に嫁がせました。昭和四十九年に長男を出産し、浄妙寺において子供の御授戒をしていただきました。当時、夫や夫の家族は「寺信心をしてはいけない」と、私がお寺に行くのを反対しました。その頃は、何のことか理解できませんでした。毎日の生活の中で意見が合わなくなり、私は離婚を申し立てました。子供を私が引き取り、何も要求しないことを条件に離婚に応じてくれました。 生まれて一カ月の赤子を連れて堺市に移り住みました。子供を保育所に預けて美容学校に通い、美容師の資格を取得しました。この頃は、毎日二時間以上の唱題と一年に二世帯の折伏を成就し、六年間で十二世帯の折伏ができました。 昭和54年脱会、法華講へ 同じ頃、学会幹部の心ない行為に不審を抱いて学会が嫌になり、毎日本伝寺に通うようになりました。信心はやめたくない、これからどうしたらよいのかと、本伝寺の御本尊様に何時間も唱題し祈っていたところ、当時執事さんだった渡瀬御尊師(現・大栄寺住職)から、学会の教義逸脱問題を教えていただき、法華講という組織があると聞き、昭和五十四年に入講いたしました。私が折伏した友人たちも法華講に入り、現在も各地の寺院で活躍しています。 その後、故郷の和歌山に帰り、長男を連れて現在の主人と再婚しました。四人の息子にも恵まれ、家族全員で朝夕の勤行、お寺の行事へ参加と充実した毎日を送りました。母と一緒に毎月の登山も十年間、参詣させていただきました。 平成六年、私が四十六歳のとき、高齢で女の子を出産しました。何よりも母が喜んでくれました。母は「やっと願いが叶った、これで安心して死ねる」と私に女の子が生まれることを十年間祈ってくれていたことを話してくれました。 翌年の三月八日、家族で登山をしたその帰りの車中で、母は私に「最後の登山になった。ありがとう。お前が一番親孝行だった」と言い、三月十日、私の御題目の声を聞きながら八十三歳で亡くなりました。無事に日蓮正宗で葬儀を済ませ、初七日の日、学会員である四人の兄嫁たちは、私が学会に入らないのなら兄妹の縁を切ると言ってきました。兄は「ごめんよ。この年で離婚されたら困るし」と言っていました。あまりの理不尽さに私は泣きました。 乳ガン、余命六カ月 それから三カ月が過ぎた頃、体調不良で病院に行きました。検査の結果、乳ガンの末期で余命三カ月、長くて六カ月と診断されました。「私の番がきた」と思いました。父が肺ガン、姉が卵巣ガン、母が白血病、兄が胃ガンで亡くなっていましたから、覚悟はできていました。夫や子供たちとも話し合い、命尽きるまで御本尊様の使いをして、悔いのないよう精一杯生きようと決心しました。 入院はせず、その日から毎日五時間、十時間と唱題しました。すると、不思議に折伏ができました。 ヤクルトの営業に来た人、訪ねて来た古い友人、息子の友人、近所の友人の娘、離婚問題で悩んでいた友人夫婦、私の美容院のお客さんで恋愛で悩んでいた若い女の子二人、訪ねてきた姪、偶然病院で会った知人、年配のお客さんと、気がつけば十世帯ほど折伏ができていました。 病気のほうは宣告の六カ月はとっくに過ぎて、病院に行ったところ、ガン細胞が消えて水泡になっていると先生が驚いていました。今までの人生で地獄のような思いを何度も経験しましたが、それを乗り越えてこられたのは、亡き母が毎日唱えていた御題目が心に残っているからです。すべて御題目で乗り切れたのは、信心を教えてくれた母のお陰です。 「日は西より出づるとも、法華経の行者の祈りのかなはぬ事はあるべからず」(御書 六三〇㌻) との御書の通りと確信していま す。 昨年末の折伏状況 平成十七年十二月四日の広布唱題会の後、御住職・小笠原制道御尊師が「この後も残って唱題される方はしてください」とおっしゃいました。私が娘と唱題を始めると、谷川さんと女子部長の高坦さん親子、壮年部の向井さんも一緒に参加され、昼まで三時間の唱題をしました。 午後から私と娘は、谷川さん夫妻と一緒に折伏に出かけました。 はじめに、私が折伏した上道君の家に行きました。私は上道君に「有田市にいるお母さんを折伏して早く親孝行しよう。今から行こう」と言うと、「夜勤で帰って来たばかりだから」と言うので、近いうちにお母さんに会いに行こうと約束をしました。 次は近くに引っ越してきた七森さんのお宅に行きました。いろいろと信心の話を聞いていただき、七森さんは入信を決意され、十二月十日に娘さんと二人で御授戒を受けて内得信仰を始められました。 十二月二十七日の夜、主人から京橋の飲食店で待ち合わせの電話があり、私と娘は喜んで車で向かいました。そこで片桐さんを紹介されました。彼は「加藤さんと兄弟として付き合いたい」と言うので、私が「うちと付き合うのなら日蓮正宗の信心を理解していただかないと、よいお付き合いができませんよ」と言うと「日蓮正宗とは何ですか」と尋ねられました。話を聞くと、二年前に奥さんを亡くされて息子さんたちは独立しているため今は独り暮しとのことです。先祖代々禅宗だと聞き、間違った宗教は不幸の原因であり幸せになれないことや、私の今までの体験を話しました。すると「同じ乳ガンで僕の嫁さんは死んだのに、何で奥さん生きてるねん」と言って泣き出しました。それから仏法の話を聞いていただき、「一日も早く亡くなった奥さんの成仏を願って回向してあげましょう」と言うと、「一緒に信心させてください」と、翌日にお寺に行く約束をしました。 翌朝九時頃、片桐さんが家に来ました。「午後一時に御住職と約束したのに」と言うと「夕べは興奮して眠れなかったんです。早く来たくって来てしまいました」と言い、もっと早くこの信心に巡り会えていたらと悔やんでいました。御住職よりお話していただき、片桐さんは元旦に御本尊様を御下付戴くことが決まりました。 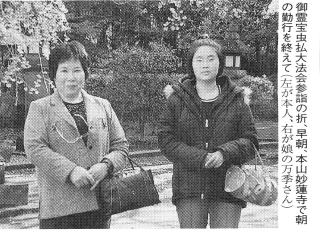 「決起の年」元旦から折伏成就 年が明けて今年の元日一は、片桐さんと一緒に、東京で世帯を持った四男が御本尊様を御下付戴き嫁の御授戒もしていただきました。一月四日の初登山会には片桐さんも私の家族と共に参加され、御開扉のとき奉安堂の中で涙が止まらなかったと感激していました。 翌日には大雪の中を東京に行き、四男の御入仏式ができました。 一月十五日、覚法寺で広布推進会のあった日のことです。そこに上道君のご両親が来られていたのですが、八年も会っていなかったので、私はすっかり顔を忘れていました。そこへ御住職の「上道君は最近来なくなったけど」の言葉で思い出し、上道君のお母さんに「八年も会っていないので感じが変わって判らなかった」と言いました。彼女は「長い間御無沙汰しています。苦労したので顔が変わって判らなかったでしょう」と言って泣きました。聞くと、上道君からは信心の話は聞いていたのですが、その当時は悩みもなく幸せだったので、考えてみると言ってそれっきり八年も経ってしまったそうです。上道君のご両親は、「今回、自分たちから息子に『加藤さんに連絡して信心させてほしい』と言ったところ、『加藤さんにはお寺に行ったら会えるから、お寺に行って御住職にお願いして信心させてもらい』と言われたので来ました」と言うのです。私は今までに御縁のあった人たちの名前をお経本の後ろに貼って、朝夕の勤行で御祈念しています。そのことを伝えると、自分たちの名前を見つけてご夫婦で泣いて喜んでくれました。二月十二日、御授戒を受けて御本尊様を御下付戴いた後、有田市まで御住職に御足労いただき御入仏式をしていただきました。 次に二月十九日、仏覚寺での婦人部対象の広布推進会の帰り、同じ支部の川崎さんを車で高野口まで送って帰る途中のこと、川崎さんが「近所に折伏したい人がいる」と言うので「今から行きましょう」と言って、前垣さんという方のお宅に伺いました。いろいろと信心の話や私の体験など聞いていただきました。前垣さんは、素直に入信を決意され、三月五日に御本尊様を御下付戴き、御入仏式もできました。 三月十二日には、片桐さんが母親に信心をさせたいと御住職にお願いして、片桐さんのお母さんが御授戒をお受けしました。この日は一月に生まれた二人目の孫も一緒に御授戒をしていただきました。 御法主日如上人猊下は、 「大御本尊様という最高の縁に出値うことによって、仮りに我々がいかなる悪業の因を積んでいたとしても、妙法蓮華経の偉大なる功徳によって変毒為薬し、煩悩即菩提、生死即涅槃、娑婆即寂光と変えていくことができるのであります。ここで大事なことは、善き縁に出値うということであります」(大白法 六八五号) と御指南あそばされています。今まで縁のあった人たちには必ず仏法の話を聞いていただき、それが縁となって入信されています。毎日元気に仏様のお使いをさせていただける喜びにあふれ、苦悩に満ちている多くの人たちを日蓮正宗に縁させてさしあげる役割が私の使命と感じ、「『立正安国論』正義顕揚七百五十年」に向かう「決起の年」、御法主上人猊下の御もと、法華講員としてこれからも御住職のもとに折伏にがんばってまいります。 |